労務管理とは?人事管理との違い・目的・仕事内容などを解説
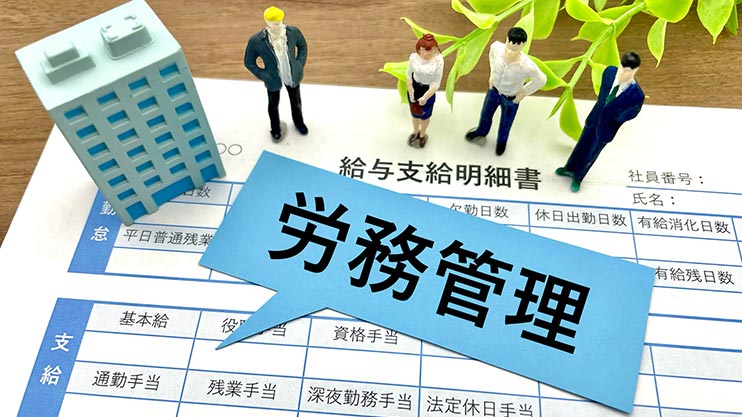
更新
労務管理とは、勤怠管理や給与計算、福利厚生の管理など、従業員の労働条件や環境に関する業務全般を指します。職場環境を改善し、従業員の業務効率を上げるためには欠かせない業務です。働き方の多様化が進む中、労務管理の果たす役割は日に日に大きくなっています。
労務管理には多様な役割があるために、具体的にどの仕事を指すのかわからない人が多いかもしれません。本記事では、労務管理の基礎知識から、求められる能力・意識までを詳しく解説します。
労務管理とは職場環境を管理する業務のこと
労務管理とは、従業員の労働条件や職場環境などを管理する業務です。企業の経営資源には、人材や資金、情報、時間、知的財産などがあります。そのうちの人材、つまり従業員の労働に関する事柄を管理するのが労務管理の役割です。
業務範囲は、就業規則の作成、労働契約の管理、従業員の勤怠や給与計算、福利厚生の管理など多岐にわたります。企業規模の大小にかかわらず、従業員を雇用しているすべての企業にとって、労務管理は非常に大切なものです。
労務管理と人事管理の違い
労務管理と混同されやすいのが、人事管理です。労務管理と人事管理はどちらも人材に関するバックオフィス業務ですが、一般的には区別されています。
労務管理は、法律にもとづき就業規則の作成や社会保険の手続き、職場環境の改善など組織単位の事務手続きを行う業務です。労使の雇用関係や労働条件にかかわる管理を中心に行うのが特徴です。
その一方で、人事管理は人材の評価や採用、育成など従業員個人にかかわる業務を担当します。人事管理の主な目的は、社内の人材をより効果的に活用することです。なお、企業によっては、人事担当と労務担当を兼任している場合もあります。
労務管理と勤怠管理の違い
勤怠管理は労務管理の業務の一部です。労務管理は、従業員の労働環境に関する業務全般を指します。それに対し勤怠管理の仕事内容は、出退勤時間や休憩時間、時間外労働、有給休暇の取得日数などの管理です。
例えば、勤怠管理によって長時間労働の実態が明らかになった場合、労務管理において人員配置の見直しや労働時間の適正化などの対策が必要になります。両者には担当範囲と役割に違いがありますが、適切な労務管理には勤怠管理が欠かせません。
労務管理の目的
事務的な手続きをすることだけが労務管理の目的ではありません。効率的な管理によって生産性を高めたり、コンプライアンス遵守によってリスクを回避したりすることも重要です。
効率的な管理による生産性の向上
労務管理の目的の1つは、労働条件や労働環境の効率的な管理を通じて生産性の向上を図ることです。具体的な例としては、職場環境の整備や適切な給与計算と管理、従業員の健康維持等の把握が挙げられます。
働きやすい職場を実現することで従業員のモチベーションが上がり、業務の効率アップが可能です。結果として企業価値が上昇し、優秀な人材の獲得や顧客満足度の向上などの好循環にもつながります。
コンプライアンスとリスク回避
コンプライアンスとリスク回避も労務管理の大切な目的です。企業には社会的責任があるため、法令や社会的規範に従って業務を行うコンプライアンスが重視されます。例えば、労働環境や労働条件、就業規則、従業員の健康維持などでは、法律に則った正しい管理が必要です。万が一、法令違反をしてしまうと処罰の対象になるうえ、企業の評価や信頼の低下につながるリスクがあるためです。
また、安全・安心な職場環境を維持できなければ、従業員の健康に悪影響を及ぼしたり、社内トラブルを招いたりする可能性もあります。そのような事態を避けるために、適切な労務管理が不可欠です。
労務管理の仕事内容
就業規則作成から従業員の勤怠管理や給与計算まで、幅広い業務を担うのが労務管理の特徴です。労務管理の業務範囲と具体的な仕事内容を紹介します。
就業規則の作成・管理
就業規則や賃金規程のような社内規程の作成・管理も、労務管理業務の1つです。常時10人以上の従業員を雇用する企業(事業場)では、労働基準法の規定により、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。従業員数10人未満の場合は義務ではないものの、企業のルールを明確にして労働トラブルを防ぐために、就業規則の作成が推奨されています。
就業規則の作成にあたっては、各事項を漏れなく記載し、内容変更の際にも届出が必要です。就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、企業で制度を定める場合に必要な「相対的必要記載事項」があります。目的や適用範囲を企業が規定できる「任意的記載事項」も必要に応じて記載します。
絶対的必要記載事項
就業規則の絶対的必要記載事項は以下の3つです。
- 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切り・支払の時期・昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
絶対的必要記載事項は、必ず記載しなければなりません。不足している事項があれば労働基準法の罰則規定により30万円以下の罰金の対象となります。
相対的必要記載事項
就業規則の相対的必要記載事項は以下のとおりです。
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
相対的必要記載事項は、企業で制度を定める場合に記載する必要がある事項です。退職手当や安全衛生など、企業が独自に定めている制度・ルール等に挙げられます。
任意的記載事項
任意的記載事項には、以下のような事項を諸規程などで定めるのが一般的です。
- 応募や採用に関する事項
- 副業の取り扱いに関する事項
- 出張旅費に関する事項
任意的記載事項の記載について、法的な作成義務はありません。企業理念や就業規則の解釈、副業の取り扱いなど、必要と思われる事項を企業の判断で記載します。
労働契約に関する管理
労働条件通知書や雇用契約書を作成したり、トラブルが起こらないように管理したりするのも、労務担当者の大切な仕事です。従業員を雇用する際は、労働基準法によって、労働条件通知書の交付が義務付けられています。また、労働条件通知書と雇用契約書を兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」を発行するケースもあります。
労働条件通知書にも就業規則と同じように、必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」と、制度として定める場合に必要な「相対的明示事項」があります。労働条件通知書と雇用契約書を兼ねる場合も、これらの項目の記載が必要です。
絶対的必要記載事項
労働条件通知書の絶対的必要記載事項は以下のとおりです。
- 労働契約の期間
- 就業場所
- 従事する業務の内容
- 始業時刻と終業時刻
- 交替制のルール(労働者を2つ以上のグループに分ける場合)
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 休憩時間、休日、休暇
- 賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
- 退職や解雇に関する規定
パートやアルバイトなどの短時間労働者、および契約社員などの有期契約労働者の場合は、以上の事項に加えて昇給・退職手当・賞与の有無や、雇用に関する相談窓口等についても記載しなければなりません。
また、法改正により、2024年4月1日から新たな明示事項が3つ追加されました。- 就業場所・業務の変更の範囲(すべての労働者が対象)
- 更新上限の有無と内容(有期契約労働者が対象)
- 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件(有期契約労働者が対象)
変更の範囲とは、転勤や配置転換で変更される可能性がある就業場所や業務のことです。例えば将来的に転勤の可能性がある場合は、変更後の就業場所や業務の内容を具体的に明示しなければなりません。
有期労働契約の場合には、契約の締結時と更新時に、更新上限の有無および内容の明示が必要です。また、無期転換(有期労働契約を一定期間(通常5年)以上続けた労働者が、希望すれば無期労働契約に転換できる制度)申込権が発生する契約の更新時には、無期転換を申し込む権利がある旨と、転換後の労働条件を明示する必要があります。無期転換申込権とは、同一企業での契約が通算5年を超えた場合に、労働者からの申込によって無期労働契約に転換できる権利のことです。参照:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます![]() 」
」
相対的必要記載事項
以下の事項が労働条件通知書の相対的必要記載事項に該当します。
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲
- 退職手当の決定・計算・支払の方法
- 退職手当の支払時期
- 臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、奨励加給、能率手当等について
- 賞与その他、最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させる食費、作業用品など
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練制度
- 災害補償・業務外の傷病扶助制度
- 表彰や制裁の制度
- 休職に関する事項
相対的必要記載事項は絶対的必要記載事項とは異なり、必ず明示するものではありません。退職手当や賞与、最低賃金額、表彰など、企業独自の制度を定める場合に、労働条件通知書への記載が必要です。
法定三帳簿の整備
法定三帳簿の作成と管理も、労務管理の大切な仕事です。「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つの帳簿を総称し、法定三帳簿と呼びます。従業員を1人でも雇用する場合は事業場ごとに作成し、原則5年間(経過措置として3年間)保存しなければなりません。
労働者名簿
労働者名簿は、従業員の氏名や生年月日、性別、住所などの個人情報を記録する帳簿です。法令で定められた記載項目の他、企業が従業員を管理するうえで必要な事項を任意で設けることもできます。保存期間は、労働基準法により、従業員の退職・解雇・死亡の日から5年間(経過措置として3年間)と定められています。
賃金台帳
賃金台帳は、従業員一人ひとりの賃金の支払状況をまとめた帳簿です。従業員の氏名や性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数の他、基本給や手当などの事項を、賃金支払のたびに記載します。保存期間は、労働基準法により、賃金について最後に記入した日から5年間(経過措置として3年間)と定められています。
出勤簿
出勤簿は、従業員の出退勤に関する状況を記録する帳簿です。記載事項は、出勤日や労働日数、始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働を行った日付や労働時間などです。保存期間は、労働基準法により、従業員が最後に出勤した日(最終出勤日よりも賃金支払期日が遅い場合は賃金支払期日)から5年間(経過措置として3年間)と定められています。
勤怠や給与の計算・管理
従業員の勤怠や給与の管理も労務管理の仕事です。具体的には、従業員の始業・終業時刻、時間外労働(残業)、休日出勤、遅刻・早退・欠勤、有給休暇などの勤怠管理が挙げられます。勤怠データや人事考課のデータ等を基に、給与や各種手当、賞与を計算します。給与計算を行う際には、税金や社会保険料などの控除額の計算も必要です。
勤怠の記録と管理は給与計算だけでなく、日々の勤務実態を把握するためにも重要です。企業は安全配慮義務が課せられている観点から長時間労働や過度な連続勤務を防ぎ、従業員の健康を維持するには欠かせない業務です。
福利厚生の管理
働きやすい職場づくりに努める労務管理では、福利厚生の管理も重要な仕事の1つです。福利厚生は、法律によって義務付けられる「法定福利厚生」と、各企業が任意に導入する「法定外福利厚生」の2種類に大きく分けられます。
法定福利厚生の代表例は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、子ども・子育て拠出金などの各種社会保険です。法定外福利厚生には、社宅の提供や社員食堂の運営、育児支援、特別休暇などが該当します。いずれの福利厚生の管理も、労務管理業務に含まれます。
従業員の安全衛生管理
従業員の安全衛生管理や健康管理も、労務管理の重要な仕事です。例えば労働安全衛生法では、従業員の雇入時の健康診断や、年に1度の定期健康診断を企業に義務付けています。健康診断の実施にあたっては、従業員への周知や手配、結果の記録などの作業が発生します。
また、一定の基準に該当する事業場では、安全委員会や衛生委員会、または両委員会を統合した安全衛生委員会の設置が必要です。労務担当者は、このような安全衛生管理や健康管理の実務も担います。
職場環境・業務改善
職場環境・業務改善も労務管理の仕事に含まれます。パワハラやセクハラなどのハラスメントを予防・解決する相談窓口の設置、長時間労働の是正、育児・介護と仕事の両立支援、高齢者の活躍促進などが主な業務です。現場や専門家連携を図りながら、職場環境や業務の改善を促すことが求められます。
労務管理に関する資格
労務管理全般の業務に関する代表的な民間資格が「労務管理士」です。この資格を取得することで、労働契約の締結や労働条件の変更・管理、社会保険や労働保険の手続き、給与・賞与の計算、就業規則の管理といった業務を担うための技術習得を証明できます。試験では労働基準法の基礎知識だけでなく、実務に役立つ実践的な知識が求められるのが特徴です。
また、資格取得の難易度はそれほど高くないとされていますが、合格率や具体的な試験の難易度については非公開です。
- 実施団体:一般社団法人日本人材育成協会
- 資格の種類:民間資格
- 受験資格:20歳以上(性別・学歴・職業・経歴不問)
- 合格率:非公開
- 合格基準点:70点以上で2級労務管理士として登録可能 ※不合格の場合、受講料免除で再受験可能
資格の取得には「公開認定講座」「通信講座」「Web資格認定講座」「書類審査」の4つの方法があります。このうち書類審査以外の3つの方法では実務経験が必要なく、講座を受講したのちに試験に合格すれば2級労務管理士として登録可能です。
20歳以上であればだれでも受験可能で、資格取得を支援する公式講座も整備されているため、特に初学者にとっても取り組みやすい資格といえるでしょう。労務管理に求められるもの
労務管理の仕事の範囲は幅広いだけに、求められる能力・意識も多岐にわたります。特に重要なのは以下の4つです。
法令に関する理解力
労務管理の業務を行ううえでは、労働基準法や労働組合法など、さまざまな法令に対する理解が必要不可欠です。また、各法令は、時代の変化に伴って頻繁に改正が行われます。法改正に関する情報を定期的に確認し、コンプライアンスを徹底しましょう。
労働状況・業務改善への意識
労働状況・業務改善への意識も労務管理に欠かせません。近年は、働き方や価値観の多様化に伴い、ワークライフバランスが重視されています。また、ビジネスのあらゆる場面でデジタル化が進み、仕事そのものの進め方が従来とは大きく変化しているのも近年の動向です。
このような背景から、従来の方法を踏襲するだけでは、だれもが働きやすい職場の実現が難しい時代になりつつあります。そのため、就業規則の見直しや新たな規定の策定などを通じて労働環境を改善し、職場全体の生産性を高めていくことが労務管理に求められています。
情報管理の徹底
労務管理は、従業員の氏名や住所、生年月日、マイナンバー、給与などの重要な個人情報を扱う仕事です。情報漏えいが起きないよう、管理体制を徹底し、細心の注意を払う必要があります。
近年は紙ではなく、データでの情報管理が主流になりつつあります。データの取り扱いに関するルールを定めるのはもちろん、セキュリティ機能が高い労務管理システムの導入も検討が必要です。
計算や手続きの正確性
労務管理には、給与計算や各種手続きをミス・漏れなく進める正確性が求められます。これらに誤りがあると、給与が正しく支払われないなど従業員が不利益を被る可能性があるため、正確な仕事ぶりが要求されます。
また、近年は社会保険の手続きをクラウド上(e-Govによる電子申請)で行うケースが増えています。それに伴い数字の入力ミスや記入欄の勘違いなどが増えているため、ただミスをしないよう意識するだけでなく、正確性を高める具体的な対策が必要です。
